| 分類: |
落葉高木〜低木(常緑もあり) |
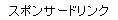
|
| 寒さ: |
強い |
| 暑さ: |
強い |
| 実期: |
5月〜6月 |
| 樹高: |
10m〜20m |
| 花径: |
1cm〜5cm(種類による) |
| 花色: |
桃色、白 |
| 場所: |
日向 |
| 水やり: |
庭木(普通) |
| 肥料: |
骨粉入り固形油粕など |
| 花芽分化: |
7月頃〜 |
| 用途: |
庭木、鉢植え(一部の品種)、切り花 |
| 花言葉: |
優れた美人、精神美
シダレザクラ(優美)
ヤエザクラ(理知に富んだ教育) |
毎年、桜の開花とともに本格的な春が始ります。北半球に多くの種類が分布しており、日本ではソメイヨシノを中心に、シダレザクラ、オオシマザクラ、ヤエザクラ、ヤマザクラ、カンヒザクラ、ジュウガツザクラ、カワヅザクラなど、自然交配されたものだけで100種類以上が分布、人工的に交配されたものを入れるとかなりの数があると言われています。
人が交配して出来た園芸品種はサトザクラと呼ばれています。
野生種
日本の野生種はヤマザクラ系(ヤマザクラ、オオヤマザクラ、カスミザクラ、マメザクラ、タカネザクラ(ミネザクラ)、オオシマザクラ、ミヤマザクラ)、ヒガンザクラ系(エドヒガン)、チョウジザクラ系があります。これらの純粋なものや、自然交配された種類が分布しています。
ソメイヨシノについて
樹高は約10m〜15m、花の大きさは約3.5cm〜4cmぐらい、咲き始めは薄紅色で次第に白色になります。植えてから早く美しい花を咲かせる事、花が一斉に咲いて一斉に散る姿もよい事から、沢山のソメイヨシノが植えられるようになりました。
種で増えない
DNAの分析などから、オオシマザクラとエドヒガン系との交配でできたという事が分かってます。また、山桜の遺伝子も混じっているそうです。種はできるのですが、自家不和合性という異なった遺伝子の桜との交配でしか実が成らないので、種を採ってまいても親と同じものが育ちません。ソメイヨシノの元は1本の樹木で、接ぎ木で増やされた同じ遺伝子をもったものが日本全土に植えられています。
標本木
桜の開花時期は品種によって少し異なります。標本木の多くがソメイヨシノなのは、遺伝子が同じで場所による気温の影響だけで開花時期が異なるからです。開花日とされるのは花が5輪から6輪以上が咲いた日になります。沖縄は暖かいのでカンヒザクラ、北海道は寒いので15か所のうち9か所がエゾヤマザクラ、根室はチシマザクラになっています。
起源の謎
江戸時代に染井村の植木屋が吉野桜として売ったのが始まりと言われています。江戸時代は園芸が盛んに行われており、人工的な交配で育てた苗を売っていたのかも知れません。最近になって上野公園にソメイヨシノと兄弟のエドヒガン系の桜が6本見つかっており、近くには同じ頃に植えられたソメイヨシノがあり、これが原木の可能性があると言われています。
名前の由来
明治時代に入ってから、藤野寄命という博物学者が上野公園でこの桜を見つけ調査し、染井村の植木屋が吉野桜と言う名前で売っていた事を突き止めました。奈良にある吉野の山桜とは異なる事から、この名前を付けたそうです。
寿命
寿命は60年ぐらいとあまり長くはないと言われており、原因はハッキリと分かっていません。樹齢100年を超えるものが、青森県の弘前公園に300本以上が残っていて、リンゴ栽培を元にした剪定技術によって今も花を咲かせています。 |
| 作業カレンダー(暖地基準) |
| 月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 開花時期 |
|
|
|
|
|
|
|
開花 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 場所 |
日向 |
| 植え付け |
植え付け |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
植え付け |
| 剪定 |
不要枝の剪定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剪定 |
| 肥料 |
寒肥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肥料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|