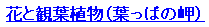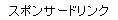| 分類: |
常緑小高木 |
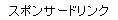
|
| 寒さ: |
強い |
| 暑さ: |
強い |
| 実期: |
9月〜10月 |
| 樹高: |
2m〜15m(種類による) |
| 花径: |
5cm〜7cm |
| 花色: |
赤、白、桃色など |
| 場所: |
日向〜半日蔭 |
| 増やし方: |
挿し木,、種まき(ポット蒔きなど) |
| 花芽分化: |
6月中旬頃〜 |
| 用途: |
庭木、鉢植え、生垣 |
| 花言葉: |
誇り、完璧な魅力
白(申し分のない愛らしさ、理想の愛)
赤(気どらない優美) |
| 通販店: |
楽天市場にあり
 |
| ツバキの仲間は日本や中国などに200種類以上の原種があるそうです。ツバキと呼ばれるのは日本のヤブツバキやユキツバキなどの他、それを母体に同じ仲間と交配された園芸品種です。山で見かける赤い花のヤブツバキは早ければ11月頃から咲き始め、1月下旬頃から3月にかけて沢山咲くようになります。園芸品種は1000種類以上があり、日向から半日陰でもよく育ち昔から庭木としてよく植えられています。 |
| 作業カレンダー(暖地基準) |
| 月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
| 開花時期 |
開花 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
開花 |
| 場所 |
日向〜半日蔭 |
| 種まき |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
種まき |
|
|
|
|
|
|
| 植え付け |
|
|
|
|
|
|
植え付け |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
植え付け |
|
|
|
|
|
|
| 植え替え |
|
|
|
|
|
|
|
|
花後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 挿し木 |
|
|
|
|
|
|
挿し木 |
|
|
|
|
|
|
|
挿し木 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 剪定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
花後 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 肥料 |
寒肥 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
肥料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 鉢の水やり |
鉢土の表面が乾けば与える |
|
ツバキの豆知識
いろいろなツバキ
日本のヤブツバキやその近縁種、園芸品種がツバキと呼ばれています。ヤブツバキは青森県以南に分布、近縁種のユキツバキは東北から北陸地方の日本海側で標高が300m以上ある谷間、双方の中間にはユキバタツバキが分布しています。これらを母体に同じ仲間と交配された園芸品種が1000種類以上あり、花は単色から色の混じった絞りや覆輪、形も筒咲きや絞り咲きなどの他、一重や八重もあるので多くの咲き方があります。大きさもいろいろで、海外で改良されて日本に輸入された洋種ツバキと呼ばれる、八重で大輪の豪華な品種もあります。他に芳香のあるヒメサザンカとの交配で作られた香りのある品種もあります。
| ヤブツバキ |
港の春 |
ティファニー |

一重の筒咲きで中輪 |

香りツバキで一重の猪口咲きで小輪 |

洋種ツバキで八重の大輪 |
| 玉之浦 |
岩根絞 |
衆芳唐子 |

一重の筒咲き〜ラッパ咲で覆輪の中輪 |

八重で絞り咲きの大輪 |

唐子咲きの中輪 |
1本から異なった花が咲く枝変わり
ツバキは突然変異で枝変わりという、異なった花が咲く枝が発生する事があります。例えば絞り咲きと単色の花が混じったり、八重と一重の花が混じって咲いたりします。プリンセス雅子はイカリ絞りから枝変わりした覆輪の咲く枝で作った品種で、皇太子雅子様にあやかって名付けられました。覆輪が咲くのは不安定で、写真は先祖返りしてイカリ絞りが咲いています。

枝変わりした不明の品種 |

枝変わりした草紙洗 |

枝変わりから作られたプリンセス雅子 |
同じ仲間のサザンカ
サザンカはツバキと同じ仲間なので、葉だけで見分けるのが難しいです。花が11月から12月頃に咲いていればサザンカ、1月から4月頃に咲いていればツバキと区別するのが一番分かりやすいです。ですがツバキの中でも12月頃から咲いて区別できないのもあります。その時は木の下に落ちた花がらで見分けられる事があります。ツバキの花がらは花首からポロリと落ち、サザンカは花びらが1枚ずつバラバラと落ちて見分けられます。

ツバキは花首から落ちる |

サザンカは花びら1枚ずつ落ちる |
ツバキ油
主にヤブツバキの種から取られています。オレイン酸が多く含まれ体によい事などで食用油にされたり、保湿効果が高いので石鹸やシャンプーなどの成分として配合され販売されています。歴史は古く奈良時代に遣唐使が唐帝へ献上したという記録があるそうで、不老不死に効くと信じられていたそうです。日本では髪油、機械油、さび止めなどを目的に昔から利用されていたそうです。種は丸い実の中に入っていて、9月から10月頃に熟すと割れて出てきます。種の中に油分があり、うちで実ったものを割って見てみると栗のようで触るとスベスベとしていました。家庭で取る方法はあるのですが容易でなく、1kgで200gぐらいしか取れないので量が必要になります。

実 |

種 |
ツバキの育て方
苗の植え付け

植え付け |
時期は3月〜4月頃、秋の9月中旬〜10月頃に行えます。場所は西日を避けた日当たりのよい所から午前中の日光が当たるような半日蔭に植え付けます。耐陰性がありますが、ある程度日が当らないと花つきが悪くなります。根着くまでに2カ月以上かかるので、その間は水切れに注意します。夏の暑さと冬の寒さを和らげるため、春植えの場合は秋まで、秋植えの場合は翌年の春まで寒冷紗で保護するとよいです。
肥料
庭では2月と秋の9月頃に骨粉入りの固形油粕などを与えます。
花後の剪定

春にある新芽が伸びてよく花が咲く |
自然の樹形で放任した方がよく咲きます。樹形を整えたい場合は花後の3月下旬から4月中頃に深い剪定を避け、伸び過ぎた枝だけを切ったり、込み過ぎて風通しが悪くなった枝を元から切るぐらいと軽めにした方がよいです。来シーズンの花は枝先や葉の付け根にある新芽が伸びて付く事が多いので、その芽をできるだけ残しておくようにします。また、時期が遅くなって新しく伸びた枝を切ると花が付かなくなるので注意してください。
チャドクガの被害
蛾の幼虫の毛虫で、年によって4月から6月頃、7月から9月頃に群れて葉が食べられる事があります。長い毛の他に0.1mmぐらいと短い毒針毛が数十万本あり、刺されると赤いブツブツができて強いかゆみに襲われます。とても厄介な事に直接触らなくても、風で飛んだ毒針毛に触ったり、落ちた所に座るだけでも被害にあう事があります。また卵、抜け殻、成虫にも毒針毛があるのでこれも厄介です。刺されて症状がひどい場合は病院へ行って薬を貰った方が早く治ります。
予防する方法

オルトラン液剤 |
年に2回発生する事があるので、発生させない事が大切です。毎年4月から5月、7月から8月にオルトラン液剤を株元にまいておくと効果があります。この薬剤は葉に散布するのではなく、根から薬剤を吸い上げるので植物全体に殺虫効果があります。液剤は水で薄めて株元にまきます。
駆除する方法
毛虫に対応した殺虫剤で死にますが、落ちる際に毒針毛が風で飛んで被害にあったり、落ちた死骸にも毒針毛が残ったままなので、長雨で流されるまで周囲に近づけません。そこでチャドクガ毒針毛固着剤というのが売られているので、発生してた所にスプレーして固め、枝ごと切ってゴミに出す駆除方法です。強風の日は避け、皮膚が露出しない服装で駆除します。
挿し木で容易に増えます
方法と時期
春から伸びた新しい枝を梅雨の6月下旬から気温の高い8月頃に挿すと着きやすいです。まだ気温の低い3月から4月上旬頃にも古い枝を挿して発根させる事ができます。葉が3枚ぐらいついた長さ10cmから15cmぐらいの挿し穂を用意します。下の節の葉を取り除き、水の入った容器に20分ぐらい水揚げして、平鉢などに鹿沼土(細粒)7、ピートモス3などに挿すとよいです。
| 3月中旬 |
5月下旬 |

挿し穂 |

平鉢に挿し木 |

発根して葉が伸びてきた |
鉢上げ
翌年の3月頃になったら鉢上げします。鉢から根鉢を取ったら一つ一つ根を解いて、用土は赤玉土、鹿沼土、腐葉土の等量など、排水と通気性のよい弱酸性土を使用て鉢上げします。その他は挿し木のページを参考にしてください。
| 1年後の3月 |

伸びた新しい葉 |

鉢から抜いて一つ一つ根を解きました |

鉢上げしました |
鉢植えの管理

挿し木から3年後の蕾 |
夏以外の日差しの緩い時期は日当たりのよい所、夏になって日差しが強くなったら半日蔭で育てます。水やりは鉢土の表面が乾いたら与えます。 肥料は4月、6月、9月頃に骨粉入りの固形油粕などを与えます。小さい時に庭に植えると根付かない事があるので、開花するまでの3、4年は鉢植えで育てるとよいです。それまでは毎年3月頃に一回り大きな鉢に植え替えるとよいです。
種まきもできます
増やすのは挿し木が容易です。種まきは別の品種と交配して新しいものを作る時に行われます。種は採ったらすぐに箱やポットなどに蒔きます。覆土は3cmぐらいして、乾き過ぎないように注意します。発芽したら仮植えして苗木を作ります。
|